 2016年12月9日
2016年12月9日
『ふきのとう』『こごみ』『たらの芽』入荷しました!!
ふきのとう
雪解けを待たずに顔を出す春の使者。一番早くでてくる山菜です。独特の香りとほろ苦さが春の息吹を感じさせます。 「春の皿には苦味を盛れ」と言います。 冬の間にたまった脂肪を流し、味覚を刺激して気分を引き締めて一年の活動をスタートさせます。 冬眠から目覚めた熊は最初にフキノトウを食べるとか???
こごみ
わらび・ぜんまいと同じシダの仲間です。形はぜんまいに似ていますが綿毛はなく、薄い緑色の軸(葉柄)と薄緑の葉が特徴的な山菜です。東北地方では代表的な山菜の一つです。
クセのない万人に好まれる味で、歯ごたえがあり、噛むとわずかにぬめりがあります。色が変わりやすいので、サッと茹でておひたしやあえものに。シダ類にしては珍しくアクがないので生のまま油炒めや天ぷら、煮物、汁の実などにも利用ください。
たらめ
山菜と言われたら、まずこれを思い浮かべる人も多いはずです。
野趣に富んだ独特の香りと、ぼってりとした脂っこさが特徴です。はかまを外し、揚げ物以外は茹でてから使用しましょう。胡麻や胡桃(くるみ)、ピーナッツであえると濃厚な味が引き立ちます。野菜や鳥肉などとホイルで蒸し焼きにしても良いです。天ぷらなどはアクで油が疲労するので、一番最後に揚げましょう。
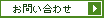
|

|